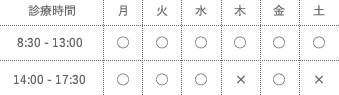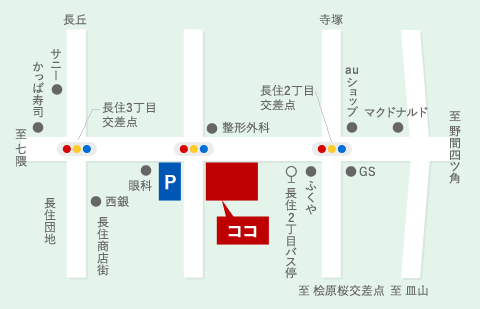糖尿病:合併症:腎症 合併症

現在、新規で人工透析導入される原因の一番の理由は糖尿病性腎症です。
しっかり治療すれば進行を抑えることが可能です。定期的にどの段階であるか定期的に調べる必要があります。
定期的な採血・尿検査で腎症の有無を検索します。
検尿:蛋白尿の有無を調べます。初期の腎症の確認には、微量アルブミン尿の有無を調べます。
採血:腎機能をみる項目として、クレアチニン(Cr) 糸球体濾過量(GFR)シスタチンCがあります。
腎症の症状として、 “むくみがでる” “体がだるい”などがありますが、これはかなり“進行しておきる”症状です。
糖尿病性腎症病期分類
第1期 (腎症前期)正常アルブミン尿(30 mg/g・Cr未満)
第2期 (早期腎症期)微量アルブミン尿(30~299mg/g・Cr)
第3期 (顕性腎症期)顕性アルブミン尿(300mg/g・Cr 以上) あるいは 持続性蛋白尿(0.5g/gCr以上)
第4期 (腎不全期) GFR(eGFR): 30ml/min/1.73㎡未満
第5期 (透析療法期) 透析療法中
(糖尿病性腎症合同委員会より)
腎症を予防する治療とは?
医師から腎症について説明をどのようにするでしょうか?例えば
“尿から蛋白がでるようになってます”
“尿から蛋白の前段階である微量アルブミンががでています”
“クレアチニンがあがっています”
“GFRが30しかないですよ”
いずれの段階でも、治療の前提があります。
1:適切な運動
2:適切な食事 腎臓病の進行に伴い、適正な蛋白やカロリーが変わります。またカリウム制限の話も行います。
3:適切な血糖コントロール
4:適切な血圧コントロール 実は腎臓機能が落ちてくると、血圧コントロールが不良になることが多いです。
その一方で血圧は130/80(家庭血圧125/75)未満で治療することが
腎症増悪の予防に重要です。血圧の治療が非常に重要になります。